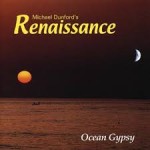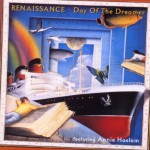英国のプログレッシブ・ロック・バンドRENAISSANCEの2000年作Tuscanyから13年ぶりとなるアルバムGrandine Il Vento。
2009年頃からの70年代ライブ音源や映像作品リリースを発端とし、ツアー活動にEPアルバムThe Mystic and Other Storiesの発表など、他の懐メロ集金バンド達とは一線を画した現役バンドらしい活動を行ってきたRENAISSANCE。全盛期のメンバーはアニー・ハズラム(Vo)とマイケル・ダンフォード(G)のみというのは寂しい部分もあるが、マイケル・ダンフォードが新曲を書きそれをアニー・ハズラムが歌う、というスタンスはこの近年の活動を正統なRENAISSANCEとして認めさせるに充分な説得力を持っていたのは事実。
そして、ツアーを続けながら基金サイトKICKSTARTERで衣装や楽器などお宝グッズと引き換えに基金を募り、新作の制作を進めているという情報も、現役バンドRENAISSANCEの復興に心躍らせる要因であった。
そんな中、2012年11月にマイケル・ダンフォードの悲報が・・・
活動が順調であっただけにショックは大きかったが、そんな苦難を乗り越えて新作を届けてくれた彼らにまずは賛辞を贈りたい。
ミステリアスなヴァースから感動のサビを経てインスト・パートへ至るいかにもマイケル・ダンフォードな進行を見せる12分超のオープニング・チューン#1。オルガンが入る劇的な場面切り替えも効果的で、霞がかかったようなコーラス部分も含め、70年代のヴァイブを見事に現代に蘇らせている。これでピアノがジョン・タウトの繊細なタッチでベースがジョン・キャンプのリッケンバッカーだったら、と思わず夢見てしまう。
アニーの美声をフィーチュアしたまどろみのフォーク#2。
Mother Russiaあたりを想起させる、重厚さと叙情を兼ね備えた#3。
サビのコーラスにAses Are Burningの頃の素朴さが薫る#4。
透明感ある明るいムードがNorthern Lightsを彷彿させる、イアン・アンダーソンがクセのあるフルートで客演の#5。
アコーディオン、タンゴっぽいリズムに男性(ベースの人か)とのデュエットと珍しい取り合わせの#6。
ピアノをバックにアニーとジョン・ウェットンが共演したバラード#7。ジョン・ウェットンが存在感ありすぎ。
先のEPで既におなじみの#8。マイケル・ダンフォードの未だ衰えぬ作曲技術を見せ付けたドラマティックなナンバー。ラストが少々あっさりしているのが惜しい。
事実上のラストアルバムとも言えるだけに、イアン・アンダーソンやジョン・ウェットンの強烈な個性に頼ることなく純粋にマイケルとアニーのRENAISSANCE色を出して欲しかったとの思いもあるが、楽曲自体は円熟の境地を見せるマイケル・ダンフォードの才能に満ち溢れている。
アニーは60代中盤とかなりの高齢にもかかわらず、気合の入った歌唱で高音部の伸びは往時のそれを彷彿させるものとなっている。反面、中低域の弱めの部分では若干ハリや柔らかさに欠ける印象も。しかしこれは、70年代のモヤがかかったような音像での神秘的なイメージと現代デジタル・レコーディングのによる解像度の違いからくるものかもしれない。